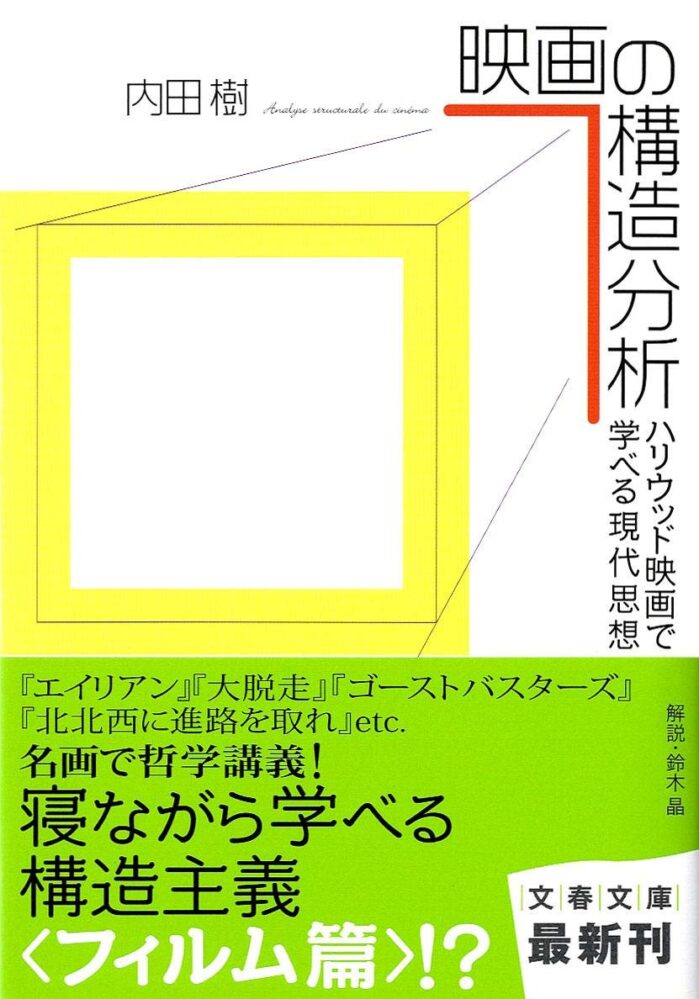本書の目的は、映画を分析することを通じてラカンやフーコー、バルトの難解な術語を分かりやすく説明することです。
映画の評論本ではありません。
映画的知識を駆使した20世紀の思想家の入門書というわけです。
クロード・レヴィ=ストロースの構造主義、ジークムント・フロイトの「精神分析入門」にも影響されています。
これらの思想家の思想を紹介しつつ、映画を構造的に分析している点が面白いと言えます。
21世紀の思想の最新潮流を元にした映画評論の本がありましたら、紹介したいと思います。
第1章 映画の構造分析
おもにジャック・ラカンの欲望論、ロラン・バルトのテクスト論についての入門的な解説を行なっています。
0 物語と構造
あらゆる物語には「構造」があります。そして物語が物語として成立するためには「仕掛け」が存在します。
「仕掛け」がなければ、ひとことも出来事を語ることができません。
この本を貫く経糸は、「知る」とは「物語る」ことであり、物語抜きの知は存在しないということです。
思考する時に、お話の枠組みを考えますが、この枠組みをクロード・レヴィ=ストロースは「構造」と名づけました。
ウラジミール・プロップは「昔話の形態学」でロシアの民話の構造分析しました。
その結果、登場人物のキャラクターは最大で七種類、物語の構成要素は最大で三十一という結論を得ました。
あらゆる物語には構造があり、構造の数は限られているのです。
この有限の構造を組み合わせて無限の物語を作り出しているのです。
1 テクストとしての映画
映画と書物の決定的な違いは、コストです。
文学作品の製作にはほとんどコストがかかりませんが、映画の制作には莫大なコストがかかります。
それゆえに映画は有料公開を前提として製作され、ビジネス的なリターンが期待されない限り、制作自体が不可能な芸術ジャンルなのです。
映画はマーケットと直結しており、観客がいなければ成立しない芸術ジャンルというのが、映画分析における出発点になります。
一方で観客に支持されたということが、興行収入や観客動員数で計測できるとも言いきれません。
大量の観客を動員しながら、心に全く残らない映画があるためです。
ここで例に出しているのが「アルマゲドン」「Xーメン」「グラディエーター」です。
逆に興行的には限定的な観客でしたが、多くの人がその映画を参照枠として文化や社会の説明に用いられる映画があります。
ジャン=リュック・ゴダールや小津安二郎の映画がそうです。
映画解釈は、その映画についての「神話作り」です。映画というテクストについての「メタ・テクスト」とも言えます。
ある映画についてどれだけの二次的な引用がされたのかも重要です。
それはその映画がある時代やある社会に「根を下ろす」ということです。
フランク・キャプラの「スミス都へ行く」は1940年代のアメリカに深く根を下ろしました。
同じくデニス・ホッパーの「イージー・ライダー」は1960年代のアメリカ人に根を下ろしました。
では、この根を下ろすような映画を狙って作ることができるかというと、そういうわけでもありません。
金のために映画を作ったが、歴史に残る傑作になったり、芸術のために映画を作ったが、とんでもないクズ映画というのもあるのです。
映画は個人ではなく、集団による創造です。そのため、映画には「作者」がいません。
ハリソン・フォードはインタビューで、自分はフィルムメーカーであり、それはチームの一員であるということだと答えました。
これは大変適切な表現であり、映画は集合体としてのフィルムメーカーによる集団的創造の産物です。
今でも多くの映画批評は「…の映画」という言葉を用いて「作者は何を言いたいのか?」を問うています。
映画に作者による「起源がある」のが前提なのですが、映画に「作者」がいるのでしょうか?
ロラン・バルトは「作者の不在」という言葉によって「オーサー」の概念を批判しようと試みました。
古典的な文芸批評では、文学作品は一義的な意味を持ち、批評はそれを探り当てることが前提になっています。
作者が作品を製作する段階で、その時に支配的だったイデオロギー、民族的エートス、宗教、先行作品、個人の価値観、美意識などなどが作品の起源を構成します。
そうであれば、起源がわかれば、作品がどんなものになるかが分かります。
しかし、バルトは「作者」の存在そのものを否定します。
そして、バルトは「作品」という言葉を避け、「テクスト」という言葉にこだわりました。
テクストは複数の要素によって織り上げられたものですので、一つ一つについて「意図」「表現しているもの」「ねらい」などの問いを立てることが不可能であり、無意味になります。
この「テクスト」を映画に当てはめると、さまざまなスタッフが関わって制作されるものである以上、多声的なエリクチュールを聴き取ることになります。
また、レフ・クレショフの「モジューヒンの実験」から分かるように、あるカットの前後にどのような映像を当てはめるかによって、映像の「意味」が変わります。
映画が1人の作者による完全なコントロール下にあるのなら「意味」を探り当てることは難しくありません。
しかし、映画には何を意味するのかわからないものが映り込んでいるものであり、それこそが映画の本質的な魅力を作り出しています。
ロラン・バルトは「イワン雷帝」を論じたエッセイで、映画記号のもたらす意味を2つのカテゴリーに分類しました。
- サンス・オブヴィ:映画の場合、映画「作者」が観客に向けて意図的に発信し、観客が労せずに意味を把握できるような意味
- サンス・オブチェ:「鈍い意味」という意味で、映画でこれみよがしに露出しているにも関わらず、ストーリーに関わりを持たないもの
「鈍い意味」は、観客がそこから「作者」のメッセージを上手く受けとることができませんが、その映画記号は観客の意識に突き刺さったまま残ります。
観客はそれを無視することもできず、しかし解釈することもできません。
意味は無意味なものに媒介されて深みを獲得していきます。
テクストを読んでいる時に意味のつながらないものに遭遇することがあります。
「意味の亀裂」をそのままにせず、「橋」をかけることで話の辻褄を合わせようとします。その橋を「解釈」と呼んでいます。
ジャック・ラカンはこれと似たことを「原因」について語っています。
原因について推論するとき、そこには論理の「断絶」があります。
何か原因が「あって」、物語が動き出すのではなく、何かがうまくゆかないとき、何かが「ない」ときにだけ、物語は語られ始めます。
映画を見て少しでも「ひっかかり」を感じるとしたら、そこには亀裂があることの徴候です。
「ひっかかり」は2種類あります。
実定的な抵抗感と欠性的な抵抗感です。
実定的な抵抗感とはバルトのいう「映画的なもの」との出会いの経験です。
最もよく見られるのが「同一物の反復」です。
この実定的な抵抗感に基づく映画の解釈は、映画の構造分析の「初級」です。
映画「エイリアン」の分析
内田樹氏は「エイリアン」を歴史的な傑作と評しています。
この映画が実に巧妙に構造化されているからです。
表層的には、最初に成功したフェミニズム映画といえます。
シガニー・ウィーヴァー演じるリプリーはハリウッド映画がはじめて造形に成功した「ジェンダー・フリー」ヒロインです。
これ以降に男性の暴力に決して屈しない自立し、自己決定するヒロインの原型となります。
そしてH・R・ギーガーの造形したエイリアンはその形状からも分かるように男性の性的攻撃の記号です。
ストーリーの水準から、フェミニスト=ヒロインを屈服させようとする家父長制的な男性性のあいだのデス・マッチという図式に展開します。
しかし、エイリアンにはもう一つ秘密があります。
「体内の蛇」という古代的な恐怖譚の現代的ヴァージョンであるということです。
ハロルド・シェクターによれば「体内の蛇」は中世以来ヨーロッパ各地に伝承されている怪奇譚の一つです。
若い女性が不注意から蛇などの異類の卵を飲み込んでしまい、卵が胃に中で成長し、異物が食道を上って外に出ようとする時に窒息して死にます。
妊娠と出産の暗喩であることがすぐに分かります。
「体内の蛇」とは母になることに対する女性側の恐怖と不安と嫌悪を表象したものです。
こうした感受性は、当の女性自身によって抑圧されることになります。
「体内の蛇」の説話は、神話学的機能は、女性であり続け、かつ女性であることを忌避する、という両立しがたい要請を両立させるという論理的アクロバシーにあります。
エイリアンではストーリーラインと映画記号の水準で異なる物語が語られます。
二つの水準による正反対の物語の働きが映画に比類なき緊張感を与えています。
エイリアンでは残り30分になってから、いきなり猛然と反-物語的なファクターの乱入が始まります。
リプリーは性的な存在者として見られることを拒否するヒロインですので、リプリーを襲う反-物語的記号は、リプリーを性的コンテクスの中に再回収し、リプリーがふつうの女性でしかないことを思い知らせようと働くことになります。
映画のクライマックスに至って、それまであらゆる因習的な性的記号性を拒否してきたはずのリプリーを猛然と性的記号の本流が襲うのです。
エイリアンは明示的でフェミニスト的な主題、下支えする古代的な恐怖譚、それらを転覆しようとする反-物語的な性的記号といった複数のファクターが重なった構造になっているのです。
2 欠性的徴候
「あるべきはずものがない」ことで覚える違和感を「欠性的な抵抗感」と呼ぶことにします。
ジョン・ミリアスの「若き勇者たち」では、あるべきものがありませんでした。
それは「理由なき反抗」から「アメリカン・グラフィティ」「クライ・ベイビー」に至るハリウッド高校生映画で自然な背景として信じ込まされてきたロックと恋愛です。
「若き勇者たち」では自然だと思ってきたことが、極めて選択的な配慮に基づく作りものであることを教えてくれました。
このようにあるはずものをあえて言い落とすことでメッセージを送ることができます。
典型的な例が西部劇です。
アメリカ近代史では南北戦争後の開拓時代には5千人の黒人カウボーイがいました。
カウボーイにはスペイン系、メキシコ系、アフリカ系、中国人、日本人もいました。カウボーイが当時のアメリカで唯一人種差別がなかった職業だからです。
しかし、ハリウッドの西部劇にはこうした人物が主要な人物として登場したことはありませんし、エキストラとしてもほとんど出現していません。
黒人カウボーイが主要な登場人物になるのは、「シルバラード」や「許されざる者」になってからです。
この商業映画が始まってから百年間の言い落としによって、アメリカの開拓史に黒人は全くコミットしていないという誤った歴史認識がアメリカ人観客の間に広く定着し、アメリカ社会に深い傷跡を残しました。
ブレーク・エドワーズの「ティファニーで朝食を」にはユニオシさんという日本人が登場します。
日本人ならすぐにそこには日本人がいないことに気が付きます。
しかし大多数のアメリカ人は気がつきません。そこにユニオシさんという日本人がいるからです。
映画「大脱走」の分析
欠性的徴候の例として「大脱走」の構造分析を行います。
「エイリアン」同様に、そこには重層的な構造が存在しており、ストーリーラインとは別に反- 物語的な映画記号が描き込まれているのです。
「大脱走」ではラカンが「盗まれた手紙」から読み出したのと似た「抑圧とそれを逃れる代理表象の物語」が読み出せます。
「抑圧」とはフロイトが「精神分析入門」で説明しているように、無意識から意識への間に番人がおり、意識に入ることができるものを選別していることです。
私たちは抑圧が活発に機能していることを知りません。
抑圧された心的過程はエネルギーを失わず、夢や妄想、神経症などの「症候」として再帰します。
このフロイトの「押し戻す番人」と「変装して脱出を企てる心的エネルギー」比喩が、「大脱走」の下絵を描いています。
「大脱走」は抑圧とその効果についての物語なのです。
捕虜は自分達にいちばん似ていないものに変装して外に出ることに成功します。それはトンネルです。
フロイトによれば夢においてトンネルは女性性器の象徴です。
また「大脱走」は抑圧とその効果の物語です。そこでは「父の審級」に位置する存在の収容所長が登場します。
彼の父としての仕事は二つあります。
- 母と息子を去勢の威嚇によって切断すること
- 子供に象徴秩序を習得させること
捕虜たちは「父の審級」の命令を拒絶します。
それゆえに「大脱走」は「アンチ・エディプス」、つまり「父殺し」のドラマなのです。
しかし映画では「母性の奪還」という主題は表層的にはほとんど出てきません。映画に女性が全く登場しないからです。
この「母性の奪還」のために映画で女性性について象徴的な行動を取るのが、トンネル組とでもいうべき3人です。
ポーランドから亡命してきたダニー、イギリス将校のウィリー、工作屋セジウィックです。
女性性器=産道の記号であるトンネルに関わる登場人物に女性性の役割を与えているのです。
アメリカ組の3人が共有しているのは「贈与者」という特性です。
個人の差はあっても、それぞれに母性の記号を負っています。
イギリス組の3人は父性的であり、それゆえに全員が脱出に失敗します。
トンネル、イギリス、アメリカの3組が映画の最後で迎える対照的な運命を知ると、この映画のモチーフの一つが「母性の奪還」であることが頷けるでしょう。
3 抑圧と分析的知性
「自然すぎることが怪しい」ことがあり、物語が微妙な仕方で破綻することがあります。
物語の読み手は、その破綻探し当て、そこに抑圧されたものに触れることに熱中します。
なぜ熱中するのでしょうか。
隠されているものが何であるかを知りたいからではありません。
知りたいのは「どんなふうに」隠されているかです。
「刑事コロンボ」「古畑任三郎」では、犯人が物語の最初に明らかにされます。
ですから誰が犯人であるかに興味が行くのではありません。
抑圧されたものの隠れ方と探し方について体系的な技法を教えてくれるのがジャック・ラカンです。
ラカンはエドガー・アラン・ポウの「盗まれた手紙」を題材に、フロイトの「快感原則の彼岸」の注釈を試みました。
私たちが何かを見落とすのは、不注意や怠惰のせいではありません。見落とすことを欲望しているからです。
隠れている何かを組織的に見落とすのは、抑圧の効果なのです。
存在すること、それが何かを同定を忌避することで、物語の中枢を占め、人々を支配している装置をヒッチコックはマクガフィンと名づけました。
マクガフィンは機能する無意味、あるいは無意味であるがゆえに機能するものです。
マクガフィンは映画の中心に位置して、映画の全てをコントロールする強烈な支配力を持ちますが、その正体を知ることは意味がありません。
マクガフィンの一例はヒッチコックの「ハリーの災難」に見ることができます。
映画「北北西に進路を取れ」の分析
マクガフィンの例としてヒッチコックの「北北西に進路を取れ」を分析します。
この映画におけるマクガフィンはマイクロフィルムを収めた像ではありません。
秘密工作員ジョージ・カプランその人がマクガフィンなのです。
カプランはアメリカの情報機関が敵国の諜報活動を混乱させるために作り出した架空の工作員(デコイ)です。
「北北西に進路を取れ」はこういう映画である、というような排他的な解釈を語り出すのは解釈者として自殺行為なのです。
4 「トラウマ」の物語
抑圧されたものを直接名指しすることはできません。その名づけ得ぬものをフロイトは「トラウマ」と名づけました。
映画「ゴーストバスターズ」の分析
ゴーストはトラウマのことです。
フロイトのトラウマ学説がアメリカに導入されたとき、アメリカ人は上手く飲み込むことができませんでした。
アメリカの文化史的文脈ではトラウマを語る物語は恐怖譚の形をとることになりました。
抑圧されたものが症候として回帰する時、フロイトは必ず不気味なものという形姿をまとうと考えました。
それゆえにホラー映画は「抑圧されたものの回帰」についてのアメリカ的な決着の付け方なのです。
ゴーストそのものが人間自身の欲望の代表的表象であり、その出現を激しく欲望していたというところまで踏み込んで、アメリカ映画ではじめてトラウマの本質に触れたのがゴーストバスターズです。
ゴーストバスターズの仕事は、いわば自分の右手で作り出したものを左手で破壊するようなものなのです。
ゴーストバスターズこそがアメリカが初めて生み出したフロイト的な意味での真の分析家なのです。
第2章 「四人目の会席者」と「第四の壁」
フーコーが「言葉と物」の冒頭で展開したベラスケスの「侍女たち」の解釈を再解釈することを企てています。
さて、映画は他者の視線から見られた世界の風景です。
ですが、それは一体誰の視線で見た風景なのでしょう。
視線の巧妙な切り替えによって、観客を映画の中に誘い込むことに熟達したフィルムメーカーに小津安二郎がいます。
ここでは「秋刀魚の味」の銀座の小料理屋・若松のシークエンスを例のあげています。
映画「裏窓」の分析
ヒッチコックの「裏窓」では足を骨折して身動きのできないジェフの視野は限定されています。
映画では観客が見えるはずのないものの条件がはっきりとしています。
それはジェフを見ていない目が見ているものです。
にもかかわらず、「裏窓」には登場してはならないはずの映像が何度も登場します。
ヒッチコックは観客を誤った解決に誘うために、ミステリーの用語で言う「燻製のニシン」が大好きでした。
映画はヒッチコックが本当に隠しているものを観客に明かさずエンドクレジットまで行きます。
本当に隠したかったのは、誰が見ているのか?という問いそのものなのです。
ミシェル・フーコーは、人間はそこから風景を見ている当の場所を肉眼で見ることができない、そこは「権力の座」であると語りました。
フーコーの視線論としては「監獄の誕生」が有名ですが、映画について考える時は「言葉と物」の第1章「侍女たち」が示唆的かもしれません。
第3章 アメリカン・ミソジニー 女性嫌悪の映画史
ハリウッド西部劇論にジェンダー論を加えたものです。
ハリウッドの西部劇が女性嫌悪イデオロギー(ミソジニー)で満たされていることは、ジェンダー論的に常識に属しますが、その理由を男女比率不均衡および弔いを手がかりに解釈しました。
内田樹氏が最初にアメリカ映画の女性嫌悪に気付いたのはマイケル・ダグラスによってでした。
「危険な情事」におけるグレン・クローズ、「ローズ家の戦争」のキャサリン・ターナー、「氷の微笑」のシャロン・ストーン、「ディスクロージャー」のデミ・ムーア、「ダイヤルM」のグウィネス・パルトロウなどです。
そしてハリウッド映画史上最悪の女性嫌悪映画が「私を野球につれてって」です。
内田樹氏は、女性尊重のマナーは男女比率の圧倒的な差から説明されますが、それと同じく、女性嫌悪もこの統計的事実から証明されるのではないかと考えています。
それを西部開拓のフロンティアで頻繁に見られた風景に求めました。
男女比率の不均衡状態が開拓史の全時代を通じて続きました。
そのため男女の結びつきは感情的な水準ではなく、「生活財」の確保という非情緒的な水準で看取せられていました。
フロンティアの男だけの集団に、一人の女がやってきて、一人の男が占有すると、集団に思いがけない亀裂を生み出します。
そこで人々は物語を創り出す必要に迫られます。
- 女は必ず男の選択を誤り、間違った男を選ぶ。
- それゆえに女は必ず不幸になる。
- 女のために仲間を裏切るべきではない。
- 男は男同士でいるのがいちばん幸福だ
これがアメリカン・ミソジニー物語の定型です。
この定型をハリウッド映画は執拗に反復し続けてきたのです。
「カサブランカ」から「明日に向って撃て!」を経て「バンディッツ」まで飽きることなく語り続けるのです。
初期のアメリカ映画では女性嫌悪的ではありませんでした。
女性主人公による連続冒険活劇があったのです。
1920年代にはハリウッド映画による西部劇全盛期に突入し、女性主人公はほぼ一掃されます。
奇しくもハリウッドの映画製作の始まりとフロンティアの消滅がほぼ同時期でした。
ほぼ二世紀にわたってフロンティアの全域で繰り返し語られたであろう、選ばれなかった男たちの怨念を鎮魂する喪の儀式を誰かが執り行わなければなりません。
人類学が教えるように、死者を安らかに眠らせるのは生者の重要な仕事です。
恨みを残して死んだ者を弔うことを怠ると生者に災いが降りかかるというのは、旧石器時代以来、世界中のすべての社会集団が合意に達している人類学的事実です。
現代アメリカ社会もその例外ではありません。
内田樹氏は、その祈りの一つがアメリカ文化に横溢する女性嫌悪の物語と考えています。